|
万 里 の 長 城 |
ドーナッツか あんぱんか
若 松 林 治
永輝会のご推薦により、「国際協力事業団(JICA)の中国企業技術指導」に、二00一年のほぼ一年間参加させて戴いた。
上海の北、直線距離で百㎞位の揚子江対岸にある南通市(日本の県に相当・人口八五〇万人)は、東レ・帝人等の百万㎡を越える巨大工場群をはじめ、日系企業が三百社以上進出しているという繊維工業の町で、ホテルも日本人であふれている。しかし、地場の機械工業は「人民公社」時代から続く元国営企業が多く、日野の三十年前位の水準である。
私が担当したシリンダーライナーの鋳造・加工工場は、OEMと補給部品を一日六千個生産している、社員約八百名の中規模の会社である。昔、トヨタの、故 大野副社長と鈴村主査に直接教わり(しごかれ)ながら改善した、シリンダーヘッドやカムシャフトラインの改善経過をイメージしながら、恩返しの様な気持ちで「トヨタ方式」を説明し、現場で「仕掛り山」の削減を説いた。中国のWTO加盟もあり、会社の会長に相当する共産党書記をはじめ、皆 熱心に取組み、半年で三千万円の利益をあげる等、 効果は著しい。 心配した「人員削減」等の、言葉に対する教条的な反発もなく、大幅なリストラも約束した。 無尽蔵で安価な労働力に恵まれた中国は、既に「世界の工場」であり、私達自身の「MADE IN CHINA」に対する抵抗感もなくなった。
幅十八㎞の揚子江を十分間隔・四十分で渡るフェリーの船上から見る巨大貨物船の頻繁な往来や、河口都市 上海の発展ぶりは驚嘆に値する。日本の空洞化について、中国での講話の一節、「日本の製造業を中心とした工業圏が国境を越えてアジア全体に拡散しており、日本は現在ドーナッツ現象による工場の空洞化で苦しい状態にある。しかし、技術開発の中心は日本であり続ける為に各企業は努力しており、生産管理面でもトヨタ方式自体が多彩な進化を遂げて、ドーナッツをアンパンにする努力を怠ってはいない・・・」等と、多少強がりの演説をしたのであるが、現実には空洞化の勢いは止まらない。 原因は、工場進出による生産・生産管理・品質管理等の生産実務指導が、最も有効な技術移転となって自らの空洞化を招いているのである。 JICAの技術援助も決して無駄ではないが、空洞化の寄与率としてはあまり高くない事を現地で実感した。 税金を使ってJICAの仕事をした立場としては肩身が狭い?が、ODA予算の削減もあり、今後共、民間による技術移転が中国経済発展の原動力であり続ける事は変わらない。
今回は、自動車メーカー出身者主体の「専門家」約十名と協力して指導した。
当初は「世界のトヨタ生産方式」なので、少なくとも自動車メーカー間での認識程度の差は大きくないと思っていた。しかし、実際の現場指導や議論の過程で、私達が実践してきたトヨタ方式のレベルがダントツに高い事を確認し、「日野の実力」に自信を持つ事ができた。(あらためて、天国の大野さん・鈴村さんに感謝したことであった。)中国の地場機械工業の水準はまだ高くないが、繊維同様
日本の技術を熱心に学び、月二千円で雇用できるというパート多用の高い価格競争力を武器に世界市場を目指しており
日本製品は対抗できない。 故、逆に、育成による低価格部品調達等で中国経済を強化し、その「十三億人市場」を日本の高付加価値・多様化製品の顧客とする発想で、日本経済活性化戦略の再構築が必要である。
一方で、一ドル三六〇円で日米貿易摩擦を繰返した過去と同様、中国元の「変動為替相場制」への政策転換を迫る政治課題にも注目したい。
北京経由で帰国した折、「万里の長城」を二時間程歩いた。テレビでみたそれよりも遥かに雄大なスケールに圧倒され、驚き・呆れてしまった。「徹底的な無駄排除」を標榜するトヨタ方式の熱弁をふるった数日後だっただけに、まさに「愚かな公共工事の見本」とうつったのである。
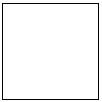 帰国して四週間後、四国の石鎚山登山で、閑散とした本四架橋を渡った。
サービスエリアから、万里の長城にもまけない現代の巨大な無駄?をまのあたりにして、ア~ァ・・
・ 。
帰国して四週間後、四国の石鎚山登山で、閑散とした本四架橋を渡った。
サービスエリアから、万里の長城にもまけない現代の巨大な無駄?をまのあたりにして、ア~ァ・・
・ 。
2001年8月
